丸三漆器の「秀衡塗」は、初代・清之助より言い伝えられている「いい物を造れ」という言葉をかたくなに守り、木地作りから加飾まで、職人の手造りによる丈夫で美しい真物の漆器です。
その工程は15以上にもおよび、熟練の職人が手間をかけ、丹念に作り上げた逸品です。
木地作り
冬期に山から切り出されたホウ、ケヤキ、トチ等の天然木丸太で椀の土台になる木地を作ります。
木地師はそれらの丸太を椀の形に仕上げていきます。漆が映えるよう、使いやすいようにと木地の形や丸み、厚み等を確認しながら仕上げまで丹念に作り込んでいきます。
特に乾燥は我や変形の原因になることから、短いものでも1年、長いものでは10年以上の期間を乾燥に費やします。

- Step1木地作り
- 冬に山から切り出されたブナ、ケヤキ、トチ等の天然木丸太で椀の土台になる木地を作ります。木地師はそれらの丸太を椀の形に仕上げていきます。漆が映えるよう、使いやすいようにと木地の形や丸み、厚み等を確認しながら仕上げまで丹念に作り込んでいきます。特に乾燥は我や変形の原因になることから、短いものでも1年、長いものでは10年以上の期間を乾燥に費やします。

下地作り
仕上がった木地に、漆をしみこませ、木地を固め、継ぎ目に和紙を張り強度を持たせます。和紙は地元で漉かれている東山和紙を使用しています。
砥の粉と漆を混ぜ錆漆を作り全体に塗っていきます。
乾燥させ、耐水ペーパーを使い滑らかに研ぎあげます。下地は次の工程である塗りの仕上がりを左右する工程なので、全行程の中で最も時間と手間がかかります。


- Step2木地固め
- 生漆を木地に塗り込みます。刷毛で丹念に塗り込み、生漆を十分吸い込ませることで、防水性を高め、伸び縮みと変形を防ぎます。

- Step3布着せ
- 木地の薄い部分や摩擦が大きい部分に麻布や木綿布を貼って補強を行い、米と水で練り込んで作る糊漆で密着させます。

- Step4布目摺り
- 糊漆が乾いたところで、布目に切り粉錆を付けます。ヘラでしっかりとしごきながら付けていき、乾燥したところで研磨します。

- Step5切り粉付け
- 木地全体にヘラで地の粉と生漆を混ぜ合わせたものを塗り、厚みをつけ、乾燥させた後、表面を平らな砥石で研磨します。

- Step6化粧錆
- 地付けと同じ要領で木地全体に切り粉錆を着けて乾燥・研磨を行います。

- Step7錆止め
- 下地面を堅牢にするために、生漆を研磨した錆面に吸い込ませます。この後研磨を行うことで塗り工程の漆の付きをよくし、下地作りは完了です。
塗
秀衡塗の塗り面は「塗り立て」、もしくは「花塗」という仕上げ方で、最後に艶出しや研ぎはありません。そのため、空気中の塵や埃が入らないよう細心の注意が必要です。
塗り面に塵や埃が付いてしまった場合は先端のとがった棒を使い「節上げ」という技法で、取り除かれます。
塗り作業は、下塗り、化粧さび研ぎ、中塗り、化粧さび研ぎ、上塗りという工程で仕上げられます。
漆塗りは高度な技術が必要な工程で、漆の硬さ、塗った厚み等、熟練の技と経験を持った職人が仕上がりを想像し仕上げます。


- Step8下塗り・中塗り
- 均一に漆がのびるように注意しながら、刷毛を様々な方向に動かしながら全体に下塗り漆を薄く塗っていきます。始めにフチ、次に平らな面と、塗る場所にも順番があります。

- Step9研磨
- 下塗りの後と、中塗りの後は漆を乾燥させて研磨を行います。研磨を行うと塗膜の凹凸がなくなり仕上がり、重ねて塗る漆の密着性がよくなります。研ぎ炭と水に浸しながら研磨を行います。

- Step10上塗り
- 朱漆等、顔料を混ぜた漆で文様を描きます。
加飾
秀衡塗の特徴となっている源氏雲と有職菱文を入れる工程です。描かれる草花紋は伝統技法である「漆絵」で描かれます。
「漆絵」は様々な色の色漆を使って描かれ、筆の勢いを使って大胆かつ繊細に描かれます。使用する色漆は、硬化する過程で変色する場合もあるため、長年の経験を積んだ職人が季節やその日の状況を見極め、風呂(漆を硬化させるための箱)で乾かす時間やタイミングを計ります。
金箔の切箔は、漆が半乾きになった状況を見極め張り付けられます。

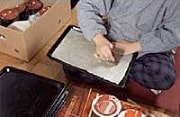
- Step11置目
- 文様を描いた和紙の裏側を顔料でなぞり、漆器に文様を写し取ります。

- Step12雲地描き
- 秀衡塗の場合、金箔を施すところは朱漆で塗りつぶします。この塗りつぶす部分を雲地と言います。

- Step13箔貼り
- 漆器を風呂に入れ、漆が半乾きになったら金箔を貼り付けます。金箔は、あらかじめ菱形に裁断しておきます。箔貼りは筆に水を含ませ、和紙の面を筆先につけてそのまま所定の位置に置きます。

- Step14上絵付け
- 朱漆等、顔料を混ぜた漆で文様を描きます。

- Step15箔止め
- 生漆を綿につけて金箔部分に擦り込み、漆の皮膜を作ります。金箔の摩滅を防ぎ、鮮やかな色合いを出すことができます。




